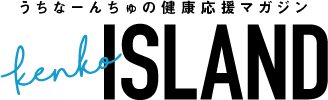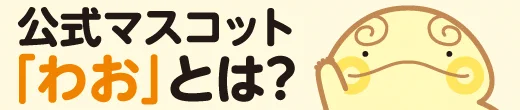老けない人は知っている、“糖化ブレーキ”習慣クイズ!
特集 2025/08/15 513 views

「老化」は避けられないものだけど、人によってその程度やスピードには差があるもの。その差を引き起こす要因の一つが「糖化」です。この記事では、kenko ISLAND71号「糖化と老化」と関連して、老けない人は知っている、糖化対策につながる知識をクイズ形式で紹介します。
(監修:昭和医科大学医学部教授 山岸昌一先生)
そもそも糖化とは?
「糖化」とは、体内で使いきれずに余った糖がタンパク質とくっつき、タンパク質の本来の働きを奪うこと。糖化されたタンパク質は最終的に老化物質「AGE」となり身体のあちこちに蓄積することで、肌を老化させたり、関節炎を悪化させたり、薄毛の原因となるなど、さまざまな症状を引き起こします。

Q1. 糖化を促してしまう飲み物は、次のうちどれ?
①炭酸水
②ミネラルウォーター
③甘い飲み物
正解は③。ジュースや甘い炭酸飲料、果実飲料などの甘い飲み物は糖分が高く、急速に糖化を進めてしまうものと考えましょう。特に、ジュースに多く含まれている「ブドウ糖果糖液糖」や「果糖ブドウ糖液糖」といった異性化糖は、ブドウ糖の10倍もAGEを発生させやすいことがわかっています。また、カロリーゼロと表記されている缶コーヒーやジュースには、人工甘味料が使われていることもしばしば。これらは砂糖の数百倍の甘さがあり、血糖値の上昇には関与しませんが、カロリーがないからといってたくさん飲むことで、甘みに対して鈍感になり、より甘いものを好むようになるという報告もあります。甘いものをよく飲む、食べる習慣は、糖尿病になりやすいだけでなく、糖化を進めてしまうのでほどほどにしましょう。

Q2. 糖化予防に大切なのは、以下のうちどれ?
①頭の洗いすぎを防ぐ
②水の飲み過ぎを防ぐ
③睡眠不足を防ぐ
→正解は③。アメリカの研究によると、平均睡眠時間が6時間以下の人は、7〜8時間の人と比べ糖尿病になる確率が1.66倍高いことがわかっています。睡眠不足の状態では、交感神経が過剰に反応し、血糖値を上げやすくするホルモンが分泌されるほか、疲労が回復せず、高ストレス状態になり、昼間の食欲も亢進することで体内でAGEが増える原因に。
糖化を防ぐには、睡眠不足を防ぐこと、良質な睡眠をとることがカギ。山岸先生によると、「人は眠りにつくときに深部体温を下げることで眠りが深くなるため、寝る部屋の温度は少し寒く感じる程度がおすすめです。また、就寝2時間ほど前には入浴を済ませ、身体を温めて熱を放出しやすい状態にしてから眠りにつくことや、就寝2時間前以降は、スマホやテレビなどの強い光を浴びないことが大事です」。

Q3. 実はAGEを増やしてしまう調理グッズは次のうちどれ?
①電子レンジ
②蒸し器
③炊飯器
→正解は①。
老化物質であるAGEは食品中にも含まれており、食品の中の糖とタンパク質の分子がぶつかり合うことで発生。加熱によっても作られてしまいます。そのため、電子レンジ加熱もAGEが作られやすいほか、電子レンジで加熱すると食品中のブドウ糖の構造が変化し、タンパク質とくっつきやすい(糖化されやすい)状態になることも分かっています。
そうはいっても、電子レンジは生活に欠かせない電化製品ですから、用途を使い分けてうまく糖化を防ぐことが大事です。山岸先生によると、「例えば、500〜1000ワット程度の出力で長時間調理するような使い方は避けること。加熱時間20分は長すぎますので、できるだけ短時間で済ませましょう」とのこと。
また、調理の際は、水分量の高い調理法(蒸す、茹でる)を選ぶのがおすすめ。水分が糖とタンパク質が反応するのを防いでくれます。反対に、揚げ物をはじめとした油を使う料理は、AGEを多く発生させます。
Q4.AGE蓄積が影響すると言われる病気は次のうちどれ?
①歯周病
②うつ
③不妊・男性更年期障害
→正解は全部。ちょっといじわるな問題でしたが、これらはAGE蓄積も関係することが研究で分かっています。歯周病は細菌によって起こる歯周組織の炎症のこと。血中のAGEレベルが高い糖尿病患者ほど歯周病が重症化することや、一部の歯周病菌はAGEの産生を促すことが報告されています。
うつは、複数の研究で、AGEリーダー(AGEを簡単に測定できる医療機器のこと)で計測される皮膚のAGE蓄積量が高い人ほど、うつ症状を持ち、うつ病のリスクが高まることが報告されています。また、AGEが高い人ほど不妊や流産の傾向が高いことや、男性の更年期障害にも関わっていると考えられています。
Q5.お母さんのAGEは胎児に影響する。◯か×か?
→正解は◯。
AGEが高い母親から生まれた生後0歳の子どものAGEを調べると、母子のAGEには強い相関関係があることが分かっており、その理由は胎盤を通じてAGEが赤ちゃんに移行しているからだと考えられています。それだけでなく、女性は生まれてくる時点で一生分の排卵する卵子を卵巣に抱えて生まれてくるので、卵巣や卵子の状態も胎児の頃の母親の栄養状態が影響していると言えます。
また、山岸先生たちの研究によると、小学校6年生以下の子どもとその母親のAGE値は相関関係にあることが分かっています。自らの食生活が一緒に暮らす子どもや孫などの次の世代にも影響する可能性が十分にあることも配慮することが大事です。

山岸 昌一先生
昭和医科大学医学部教授、医学博士。30年以上前から老化の原因物質「AGE」に着目し、研究を続けている糖化研究の第一人者。糖化や老化に関する著書も多数執筆。