いつもkenko ISLANDの公式X(旧Twitter)アカウントをご覧いただき、ありがとうございます。
現在、公式Xアカウント([@kenko_island])が、X社のシステム上の理由により一時的に凍結されています。
kenko ISLANDの不適切な操作や投稿によるものではなく、現在はX社へ確認および復旧手続きを進めています。
ご利用の皆さまにはご心配とご不便をおかけいたしますが、復旧が確認でき次第、こちらの公式サイトおよび他の公式SNSにて改めてご案内いたします。
いつもkenko ISLANDの公式X(旧Twitter)アカウントをご覧いただき、ありがとうございます。
現在、公式Xアカウント([@kenko_island])が、X社のシステム上の理由により一時的に凍結されています。
kenko ISLANDの不適切な操作や投稿によるものではなく、現在はX社へ確認および復旧手続きを進めています。
ご利用の皆さまにはご心配とご不便をおかけいたしますが、復旧が確認でき次第、こちらの公式サイトおよび他の公式SNSにて改めてご案内いたします。
毎日の食事や生活習慣が、肌や心のコンディションを左右していることを知っていますか?外見を磨くだけでなく、内側から輝く美しさを育む「インナービューティー(内面美容)」が注目されています。心身ともに健康で生き生きとした輝きを放つために、おすすめの食べ物をインナービューティープランナーの津波真澄さんに教えていただきました。
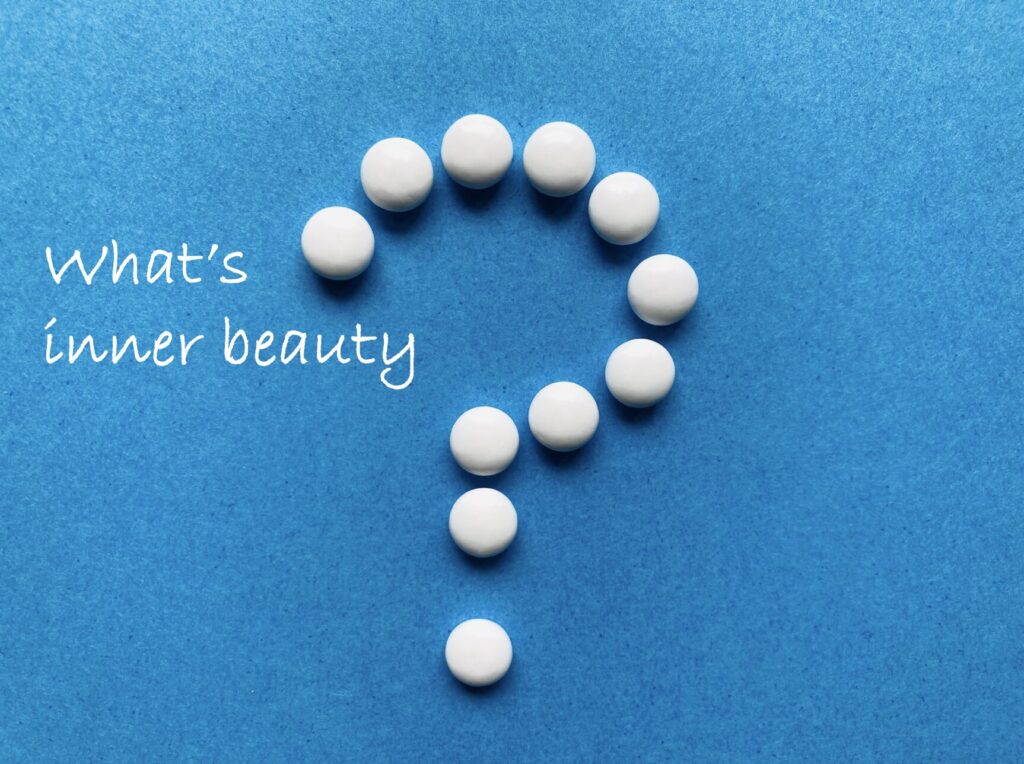
インナービューティーとは、単に見た目の美しさだけではなく、食事や生活習慣を通してからだの内側、特に腸を整え、ハリのある肌や若々しい血液から放たれる健康的な輝きを目指すことです。
また、“心の輝き”も大切な要素。毎日を楽しみながら自分を大切にして暮らしている人は、外見以上の輝きを放ちます。
「なんかあの人輝いているよね」「そばにいると元気になる」と言われる人は、心の状態が整っている証拠。心身ともに健康で美しく、人を惹きつける魅力を持つ人こそが、インナービューティーの目指す姿です。

内側から輝くためには、単に食事に気を遣うだけでなく、心身を健やかに保つ生活習慣が欠かせません。そこで注目したいのが、腸をきれいに整えることです。
腸は食べ物を消化・吸収するだけでなく、“第二の脳”とも呼ばれ、脳の次に神経細胞が集まっている場所でもあります。幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの約9割は腸で作られるといわれ、腸内環境が整うと自律神経やホルモンのバランスも安定し、自然とポジティブな気持ちが生まれるのだそうです。
からだも心も健やかに保つためには、腸を元気にすることが重要。そのため、食物繊維と発酵食品が重要なキーワードとなります。食物繊維は善玉菌のエサとなり、発酵食品は腸内環境を整えて悪玉菌の増殖を抑えるため、どちらも腸の健康には欠かせません。
特にぬか漬けは、植物性乳酸菌と野菜の食物繊維が同時に摂取できるのでおすすめです。手軽に日常的に取り入れられるので、自家製のぬか漬けを常備しておくとさらに良いでしょう。
最近は、パックに入ったぬか床に野菜を入れ一晩冷蔵庫に置くだけで、ぬか漬けが楽しめる便利なアイテムも売られているので、気軽に始められますよ。
毎日の食事で腸を整えることこそが、インナービューティーの第一歩です。

津波さんおすすめの、沖縄の暮らしに合ったインナービューティーに効果的な食品を紹介します。どれも日常の食卓に取り入れやすく、心身を内側から整えてくれます。
●納豆
日本の伝統的な発酵食品、納豆。納豆菌が腸内の善玉菌を増やし悪玉菌の繁殖を抑えるため、腸内フローラが整い、便通の改善や肌荒れ予防、代謝アップにつながります。さらに、血液をサラサラにする納豆キナーゼ、肌のターンオーバーを促進するビタミンB2・B6、抗酸化作用がある大豆イソフラボンやサポニンなど、インナービューティーにぴったりの成分が豊富に含まれています。納豆を一日一パック食事にプラスするだけで、手軽に“腸からきれい”を目指せます。
●もずく
沖縄で豊富に採れるもずくは、水溶性食物繊維が豊富で、腸内環境を整える代表的な食材です。便をやわらかくしてくれるため、腸活にぴったり。また、水溶性食物繊維は血糖値の急激な上昇を抑える働きもあり、食事の最初に食べるのがおすすめです。
●もろみ酢
もろみ酢は、沖縄が誇る泡盛りの副産物としてできる、素晴らしい発酵食品です。クエン酸とアミノ酸(必須アミノ酸9種すべてと、その他のアミノ酸9~10種類)が豊富に含まれているため、疲労回復や代謝促進、美肌効果などが期待できます。1日30mlほどを目安に、炭酸割りやスムージーに入れるなどして飲むと美味しくいただけます。アミノ酸は旨味の素でもあるため、もずくにかけたりとお酢の代わりに料理に使うのもおすすめです。酒造所によって風味が異なるので、いろいろ試してお気に入りのもろみ酢を見つけてみてください。
●シークワーサー
柑橘類はビタミンCが豊富ですが、シークワーサーにはノビレチンやタンゲレチンといった抗酸化・抗炎症成分も含まれています。ビタミンCはコラーゲン生成を助けるため、肌のハリやトーンアップも期待できます。もろみ酢をかけたもずくにシークワーサー果汁を加えると、最強のインナービューティーフードになります。皮に最も多く栄養が含まれているので、スムージーを作る場合、強力なブレンダーであれば丸ごと入れ、皮も種も使うと余すことなく栄養を摂取できます。また、皮は枕元に置いたり、泡盛に漬けてルームスプレー代わりにすれば、香りのリラックス効果も得られ、“心の美しさ”にも働きかけてくれます。青切りは8~9月、完熟は1月頃に出回りますが、ビンやペットボトルに入った100%果汁は年中手に入り保存もしやすいので、ぜひ使ってみてください。
●緑黄色野菜
緑黄色野菜もインナービューティーの強い味方です。色が濃い野菜には、抗酸化作用の高いカロテノイドやクロロフィルが多く含まれるため、抗酸化作用が強く、細胞の酸化ストレスを和らげエイジングケアにもつながります。鉄分が豊富な小松菜、β-カロテンが豊富なニンジンは、毎日の食事でも摂りやすい野菜です。それに加えて、旬の島野菜も意識して食べるといいでしょう。老廃物の排出を促すフーチーバー、鉄分が豊富で昔から「血の薬」と呼ばれるハンダマ、食物繊維とアントシアニンがたっぷり含まれた紅イモなどがおすすめです。地元の旬の野菜は栄養価が高く、そこに暮らす人の体質や気候にも合うため、“土地のものを食べる”ことがインナービューティーの基本ともいえます。
「20代、30代からインナービューティーを意識した食事をしていれば、10年後、20年後に大きな差が出ます」と津波さん。すべてを完璧にする必要はなく、週末だけでも、“腸をいたわる食事”を取り入れてみることが大切です。
============================================
監修
津波真澄さん
発酵美〜ガン料理デザイナー。インナービューティープランナー、野菜ソムリエ上級プロ、アスリートフードマイスター1級他、食に関する資格多数。「腸から健康になる」「野菜をもっと食卓に」をコンセプトに、国内外で活動中。
〈公式ブログ〉https://ameblo.jp/masumit/
============================================

■こちらの記事もおすすめ!■
・健康で美しいカラダを手に入れよう!太らないコツ 〜食事編〜
・「腸」と「気分」の密な関係。腸内環境をととのえるレシピ